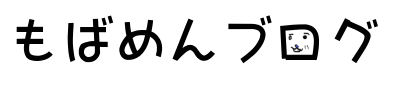仮想「普通の人」と自分を比較して落ち込むのはやめにしよう
投稿者:しんさん

仮想「普通の人」と自分を比較して落ち込むのはやめにしよう
自分自身へ言い聞かせる意味も込めて、記事にしました。
「あらゆる要素において平均以上」の人などいないということを認識し、自分の「心の形」にうまく付き合って、自分にも他者にも敬意を持って生きたいという話です。
前提条件
話が複雑になるため、ここでは善悪の定義については論じません。
何が良くて何が悪いのか、それは究極的には個々人の価値判断でそれぞれが決めることです。
解釈の話になりますが、法でさえ「これが悪だ」とは断じていないと解釈することも出来ます。
例えば、何をすればどんな刑を処されるかという事実を、善悪の定義と取るか「刑を受ける」という前提条件付きの自由だと取るかという話です。
平均という概念
前置きが長くなりましたが本題に入ります。
何か1つのモノサシで測った時に、複数のモノの平均を出すことが出来ます。
測る対象のバラつき次第で、「平均値付近の個体が最も多い」ということとは必ずしもイコールではありませんが、平均や偏差は統計的に求められることがらです。
何らかのモノサシで数値化できる事柄に対して平均や偏差という概念がついてまわりますが、簡単に数字に出来ない要素であっても「きっとこのあたりが真ん中」というポイントやエリアがあると仮定出来ます。
ヒトを形づくる要素で考えてみましょう。
「身長」や「体重」などは数値にしやすい要素です。
一方で、例えば「頭の良さ」「フットワークの軽さ」など簡単に数字には出来ません。
もう少し具体的にして例えば「どれだけ流暢に英語を話すことができるか」というところまで落としても、まだやはり数値化は簡単ではなさそうです。
しかし、そういった「簡単に数字に出来ない」要素であっても、経験や見えている範囲の事実から「なんとなく」で「この辺りが平均じゃない?」と漠然と仮置きして人間は生きています。
例えば会社員が上司に
「お前最近たるんでるぞ!」
と言われた時に
「たるみの定義とはなんですか?定量的なものですか?それは統計的な事実に基づいておっしゃっていますか?」
などと返そうものなら、恐らく社会は円滑に回りません。
仮想的な「普通」と知らずのうちに戦っているのです。
平均=普通とは限りません。
しかし、多くの場合は平均の概念が根底にあることが多いでしょう。
少し理想をこめて、実際の統計的な平均値よりも高いところを「普通」としていることもあるかもしれません。
普通の人とは
仮に人間や人格を形成するあらゆる要素が洗い出せたとします。
その「あらゆる要素」において平均値を叩き出す人が「普通の人」なのでしょうか?
なんとなくそう思えてしまいそうな話です。
しかし私は今まで生きてきた経験から「そうでは無い」と結論付けました。
各個人において突出した要素・そうでない要素って必ずあるものだと感じませんでしょうか?
「かけっこは速いけど勉強は苦手な太郎くん」
「勉強は得意だけど、おしゃべりは苦手なゆうすけくん」
程度の差こそあれ、みんな得意技と急所を持っています。
あらゆる要素が平均値の人が仮に居たとしたら、それは「普通の人」ではなく「稀有な人」です。
そして、この特別な存在を仮想の「普通の人」と考えてしまいがちなところがあります。(少なくとも私は)
仮想「普通の人」に対する劣等感
仮想「普通の人」と自分を比較すれば、劣った部分が必ず出てきます。
例えば私であれば、コンピューターを扱うことや楽器演奏は得意です。
一方で、朝が非常に弱く身体も強い方ではありません。
もちろん、自分の劣った部分を改善していくことは出来ます。
改善のためには時間を含めた各種リソースが必要で、リソースは有限です。
(ここを度外視されて根性論で語られてしまうことが非常に多い気がしてしまうのは残念なことです。)
有限リソースを何にどう割り当てるかは自由意志で判断されます。
当然、自由意志で判断した結果には各個人が責任を負いますが、過去に異なる判断をした場合の結果は想像することしか出来ません。
想像した「仮想の未来」と比較してクヨクヨ落ち込むのは建設的とは言えません。
クヨクヨするのにもリソースが必要なのです。
ですから私達は、過去の判断や選択に対しては敬意を持ち、本当の未来に目を向けて活動するべきです。
これは自分に対しても他人に対しても同じです。
「太郎くんがかけっこが速いのは、勉強する時間を削ってかけっこを頑張ったから」かもしれません。長所・短所込みで太郎くんです。
敬意は「長所・短所込みの太郎くん」に払われるべきです。
自分に対しても同様に「長所・短所込みの自分」に自尊心を持つべきです。
自分のことは深く見える、他人のことは想像する
他人には見えないことも、自分には見ることが出来ます。
「もしかしたら見えているかもしれない」と思うから他人に見られたくない部分を見せないように振る舞うのです。
見られたく無い部分の多くは、いわゆる欠点や弱点というやつですね。(弱点では無いが、プライバシーだから見せたく無いというものもあるでしょう)
それは他人も同じです。
「見せて無いから見えて無い」部分は想像で補われます。
想像で補う際に「平均」や「普通」を単純に引用しがちです。
裏を返せば、
- 仮に欠点や弱点があっても見せなければ相手は勝手に「普通」と想像することを期待出来る、だから見せないのだ
ということも言えるでしょう。
まとめ
結果として当然、他人と比較して劣等感を覚えることもあります。
この時に、相手を過大評価して自分を過小評価している可能性については考慮から漏れがちです。
うまい見せ方をした相手を褒め敬意を持つのは良いことです。
「人は鏡だ」と私は考えています。
敬意を持たれたいなら相手に敬意を持つこと。
優しくされたいなら他人に優しくすること。
いじわるな人に優しく出来ません。
人を見下す人を尊敬出来ません。
結果、「人は鏡」になるのです。
相手に敬意を持つことと自分に劣等感を持つことがセットになってしまいがちかもしれませんが、自分も鏡なのですから、自分にも一定の敬意や自尊心を保つべきです。
劣等感がバネになり、自分を高めることもあります。しかしそうでない時はあまりクヨクヨと落ち込んでも仕方ないのです。
自尊心を高め過ぎることは、ともすると他を低く見ることにつながることもあります。
しかし本来これらは切り離されたベクトルだという意識を持って、他人への敬意と自分への敬意を両立させたいですね。