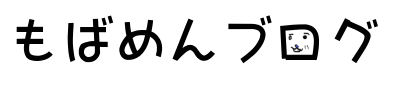早期英語教育に反対するたった一つの理由
投稿者:しんさん 2017/03/08

早期英語教育には反対
突然ですが、私は早期英語教育に反対の立場をとっています。
正確には幼少期に第二外国語を教える事に反対です。
なぜ反対なのか、その理由はシンプルにたった一つ。
「幼少期は母国語の習得をまずは第一優先にすべき」ということにつきます。
今回はこのことについて少し詳しく書いていきます。
ダブルリミテッドをご存じでしょうか?
" Double limited(ダブルリミテッド)"という言葉を聞いたことはありますでしょうか?
あるいは"Double stoped"という言葉でも置き換えられます。
これらは直訳すると
- 両方制限された
- 両方とまった
という内容になるのですが、言語学的な観点で言うと、
- 母国語・第二言語ともに不完全な状態
を指します。
例えば「日本語も英語も中途半端な状態」です。
早期英語教育をいたずらに進めてしまうことは、一歩間違えると「 日本語も英語も中途半端な子供」を生み出してしまう危険性をはらんでいます。
早期英語教育賛成派の理屈
アメリカの言語学者のノーム・チョムスキーが提唱する理論として Universal Grammar(ユニバーサル・グラマー)という理論があります。
内容を少し以下に抜粋します。
全ての人間が(特に障害がない限り)生まれながらに普遍的な言語機能 (faculty of Language) を備えており、全ての言語が普遍的な文法で説明できるとする理論。
我々人間がこの知識を獲得するためには、外界からの適切な言語刺激(一時言語データ、PLD)が必要である。
PLDには、言い間違いによる非文法的な文や会話の中断による不完全な文などの非常に質の悪いデータが多く含まれている。
それなのに、言語を獲得する子供は完全で豊かな文法を(他の能力の獲得に比べ)比較的短時間に獲得する。
ここに注目すれば、人間の言語獲得にはプラトンの問題と呼ばれる認識論的問題が存在していることは明らかである。
すなわち、獲得されたアウトプットの文法がインプットとしてのPLDよりも質的に豊かであるという問題である。
この事実は、言語を獲得しようとしている子供の脳の中に、それを可能にさせているなんらかの生得的なシステム(言語機能)が心的器官として存在していることを強く示唆している。
誤解を恐れずにざっくりと要約すると、
- 人間の脳にはユニバーサルグラマーという言語習得のための機能が備わっている
- ユニバーサルグラマーは特定の言語を対象にしたものではなく、あらゆる言語に対応した普遍的なものである
- ユニバーサルグラマーが機能するためにはインプットが必要。
- インプットは習得対象の言語での会話などの言語刺激のことを指す
といったところです。
正確にはユニバーサルグラマーとLAD(言語習得装置)に関して分けて考えた方が良いですし賛否が分かれる理論かもしれません。
ですが、難しい理屈はさておき、実際に私たち自身も「理路整然と文法を教えられたわけではないのに正しく日本語を話すこと、書くことができる」ということから、言わんとしていることは直感的に理解いただけるのではないかと思います。
そして、このユニバーサルグラマーは母国語習得の役目を終える頃、その機能が働かなくなると言われています。
言語学的に言えばクリティカルピリオドと呼ばれるもので、諸説ありますが、年齢にすると8〜10歳頃までには母国語習得の土台の部分を終えると考えています。
そして少々乱暴な言い方ですが、「ユニバーサルグラマーが機能しているうちに英語をインプットしてしまえ」というのが早期英語教育賛成派の根幹となる考え方です。
「日本語も100、英語も100」な状態は基本的にありえない
バイリンガルと呼ばれる人でも、厳密に調査をすれば「得意な方の言語」が必ず存在します。
もちろん双方が日常生活に実害無いレベルで発達する幸運なケースもあります。(幸運と言ってしまうと、学習者の努力に対して失礼かもしれませんが)
単純に数値化するのはナンセンスではありますが、便宜的に言語の習熟度を0から100までの数値で表した時に、
- 日本語100、英語75
であれば、多くの人は「まずまず良いんじゃない?」と納得するでしょう。
では、
- 日本語75、英語70
- 日本語55、英語45
といった具合だったらどうでしょう?
後者がいわゆる問題視されているレベルのダブルリミテッドな状態でしょう。
前者の「日本語75英語70」であれば、単純に足せば145です。 日本語100英語0の状態より総和は大きいと言えます。
しかし、この状態を果たして望むでしょうか?
私ははっきりNOの立場です。正直に言って「不幸せな状態」とさえ思います。
母国語の習得がきっちり終わる前に第二言語を無理やりインプットすることは、こういった不幸を生み出す危険性をはらんでいることを理解した上で、われわれは早期英語教育を考えなくてはなりません。
母国語はアイデンティティ、第二言語は道具
何かものを考えたりといった場面でも、頭の中で言語化しながら整理することは多いです。
あふれ出る感情を思わず言葉にして口に出してしまうこともあります。
単なる便利な道具に留まらず、母国語はアイデンティティを形成する上で大切なものの一つと私は考えています。
一方で第二言語はもう少し実務的な領域を担っているでしょう。
例えば、早期英語教育をおこないたい人の動機は
- 将来の職業選択において自由度を持ってもらいたい
- 日本がグローバル社会で生き残って行くために必要だ
といった道具としての側面が中心となるでしょう。
道具として身につけるのであれば、母国語の習得を含めた自我の形成がある程度進んだ後に自らの意志で、習得の目的意識を持った上で言語学習を行っても遅くありません。
たとえ仮に、第二言語学習開始が遅かったことによるハンデを後に負ったとしても、母国語の習得を妨げる危険性を強制的に子供たちに負わせることの方が問題です。
英才教育のような形で自分の子供に対して英語を初めとした第二言語を教育しようと考えている方がもしいたら、もう一度冷静に考えていただきたいです。
それは子供自身のエゴですか?あなたのエゴですか?